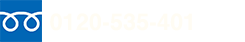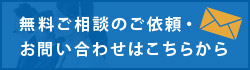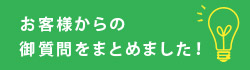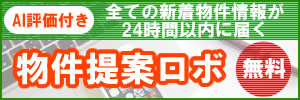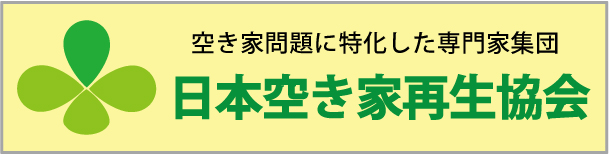- 空き家活用コンサルティング
- 相続・トラブル相談
相続対策
空き家の状態を放置することは、将来に渡って固定資産税、修繕費等の維持管理コスト負担があり、建替えて自用で使用するか、賃貸住宅等を建築して、収益不動産として保有するかを検討しなければなりません。また、相続が発生した場合の事を考え、『どの様に遺産分割するか』、『小規模等宅地等の特例』を使って相続税の負担を軽減することも視野に入れながら保有を検討しなければ、無駄な税金を納めることになります。弊社は、空家の保有リスクを最大限に軽減することを第一に次世代に財産を引き継ぐためのサポートを致します。
- ■「円満な相続」と「最適な資産の引き継ぎ」をモットーに相続対策を提案します。
空き家問題と相続対策
空き家の土地・建物を相続する際に注意しておかなければならないポイント。
- ①空き家を共有名義登記すると、維持・管理・及び賃貸・売買の際、共有者の同意が必要となります。
- ②空き家の利用状況及び相続人の保有継続要件によっては、小規模宅地等の特例を受けられなくなってしまう。
- ③空き家を放置してしまうと、資産価値が下がるだけでなく、
防犯、火災等の損害賠償責任が発生してしまうリスクがあります。 - ④空き家を相続登記をしないで、間が経ってから確認すると名義が祖父母だったり曾祖父だったりと、
所有者と相続人の関係を調べなければ変更出来ない事態になることです。

空き家等の不動産を相続する際に、相続人が複数いる場合は、共有名義で相続登記することが多く見受けられます。共有名義にした場合、空き家を賃貸したり、売却をしたりする際に、共有者の承諾を得なければ何も出来ません。その場合、相続人1人の名義にして、代償分割する等の対策をする必要があります。
空き家を相続の観点から見てみましょう。
老朽化した空き家の建物自体には、資産としての価値はありません。それでも、中にはこれから空き家になった実家の相続を控えているケースもあります。つまり、本来そこに住んでいるはずの親世代が老人ホーム等に入居し、子世代は独立して他に居を構えているケースです(※1)
この場合、子世代がその空き家の実家に住むなどの要件を満たさない限り、敷地の相続評価額が80%減額される小規模宅地の特例は適用されません。敷地は路線価などによって算出された評価額がそのまま適用されてしまいます。加えて、2015年1月1日以降は、相続税の基礎控除が引き下げられ、相続財産が【3,000万円+600万円×法定相続人の数】を超えると相続税が発生します。
基礎控除額は、相続人が子供3人の場合は4,800万円、2人の場合は4,200万円、1人の場合は3,600万円です。都市部など、土地の評価が高いエリアでは、土地だけで基礎控除を超えてしまうことも少なくないでしょう。
※1 2014年1月1日からは、介護の必要性があって老人ホームに入所した場合は、小規模宅地の特例の適用が受けられることになりました。
遺産分割の方法
遺産分割の方法には、次の3つがあります。
-
- 現物分割
- 遺産そのものを現状のままの状態で共同相続人で分割する方法です。最も一般的な遺産分割の方法です。例えば「甲土地・建物がA、乙土地がB、甲銀行の預金がA、乙銀行の預金がB」といったように。
-
- 換価分割
- 遺産そのものを分割せずに、すべて換金し、共同相続人に金銭で分配する方法です。例えば、「金銭以外の土地A等を売却して、遺産のすべてを金銭に換えます。その金銭をAとBで分配する。」といった方法です。
-
- 代償分割
- 特定の相続人が財産を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを与える方法です。例えば、「Aがすべての遺産(3億円)を相続し、その代わりにAがBに代償金(1億円)を支払う」といったように。
節税対策(課税評価を引き下げる)

空き家等を建替え等土地活用することにより課税評価を下がり節税が可能となります。建物を建てると評価額が6~7割程度になります。現金贈与でなく、親が子の自宅を建てて将来相続させる対策も考えられる。貸家を建てると5割程度の評価額(6~7割のさらに7割)になります。貸家にすると土地も8割程度の評価になるうえ、「小規模宅地等の特例」の対象にもなる。売却予定の土地は生前に更地にしておいたり測量等をしておくと、それにかかった費用分の財産が減少するめ、これも間接的に相続税の節税になります。
反面、デメリットもあります。
建物があると売却はしづらい。貸家の場合は空室リスクが常に付きまとう(収支がプラスか、借入金が返済できるか)。不動産は分けづらい財産であるため、誰が相続するかもめる原因になりやすい。生前に更地にしておけば売却しやすいが、固定資産税が上がってしまう。
不動産対策は即効性があり、かつ節税金額が大きいため効果は期待できますが、対策をしたために新たに発生するリスクも考えて、慎重に進めたいものです。
納税対策(生命保険の活用)

生命保険対策のメリットは以下のとおりです。
- ①(節税)生命保険金のうち、法定相続人の数×500万円が非課税になる。
- ②(納税)契約時に金額を確定しておけるうえ、受け取りは現金のため納税資金が確保できる。
受取人が指定でき、遺産分割協議の必要がないため、受取人は手続きだけで現金を受け取れる。注意点がいくつかあります。保険金の受取人は一般的には「配偶者」にしてあることが多いですが、納税資金確保の目的であれば、受取人は子にしておくとよいでしょう(既存の契約でも変更できます)。配偶者は法定相続分(もしくは最低でも1億6000万円)までの相続には相続税がかからないので実際に相続税を払うケースは少なく、配偶者の分の納税資金を確保する必要がないことがほとんどです。また配偶者が受取人の保険金で子の相続税を負担してしまうと、子に贈与税がかかる可能性もあります。定期保険や養老保険だと、保険金の支払われる期間が決まっているため、相続発生前に契約終了や満期になってしまうことがあります。保険料は少し高めですが、終身保険に加入する方がよいでしょう。
遺産分割でもめてしまった場合、保険金自体は遺産分割の対象ではありませんが、この保険金額の相続財産額に占める割合が高いと、遺産分割の際に考慮(持ち戻し)すること、いわゆる「特別受益」を主張される可能性があります。
現金贈与と生命保険(節税)
親から子に相続対策として現金を贈与し財産を減少させます(なお年間110万円までは贈与税はかかりませんが、相続発生前3年間の贈与は相続税の計算に加算されます)。子はこれを資金に被保険者を親、受取人を自分として生命保険に加入します。親の相続の時に子が受け取る保険金は相続税の対象ではなく、計算上有利な「一時所得」として課税されるため、二重の節税効果を期待できます。
「小規模宅地等の特例」とは

「小規模宅地等の特例」とは、被相続人が事業用や住居用にしようしていた宅地等で、一定の要件を満たすものは、80%または50%の評価減ができ、相続税の負担が軽減される制度です。
この「小規模宅地等の特例」には、
- 1.特定居住用宅地
- 2.特定事業用宅地
- 3.貸付事業用宅地
の3種類があり、それぞれの宅地ごとに要件や減額割合が設定されています。
※原則として、相続税の申告期限までに遺産分割された場合に適用され、未分割の財産には適用されません。
※相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。
相続税における「小規模宅地等」はその生活の基盤の維持等に必要不可欠のものであり、これから相続税の基礎控除は大幅に縮小される、平成27年度から相続税の申告において、被相続人の居住用財産等が「小規模宅地等の特例」が受けられるかどうかは、相続人にとって大変大きな問題となります。「小規模宅地等の特例」は、相続人の保有条件、居住要件等の要件が整わないと、特例を受けることが難しくなります。そこで、「小規模宅地等の特例」を受けるためには、計画的な事前対策が必要となります。
特例対象の宅地・免責・減額割合
| 宅地等の利用区分 | 限度面積 | 減額割合 | |
|---|---|---|---|
| 事業用 | 事業用特定事業用宅地等 | 400m2 | ▲80% |
| 事業用貸付事業用宅地等 | 200m2 | ▲50% | |
| 特定居住用宅地等 | 330m2 | ▲80% | |
適用の要件
| 特定 | 相続開始直前の用途 | 取得者の要件 |
|---|---|---|
| 特定居住 用宅地 |
亡くなった人が住んでいた自宅 | 1.配偶者、同居親族が取得 2.1がいない場合に、相続開始前3年以上仮住まいの親族が取得 |
| 特定事業 用宅地 |
亡くなった人が事業を行っていた | 亡くなった人の事業(不動産貸付事業を除く)を申告期限まで継続 |
| 貸付事業 用宅地 |
亡くなった人が不動産事業を行っていた | 亡くなった人の不動産貸付事業を申告期限まで継続 |
共同相続した場合
特例が適用できる小規模宅地等を複数の相続人が共同相続した場合は、取得者ごとに適用要件を判定します。
![[取得者] ごとに評価](https://akikatsu.net/wp/wp-content/themes/akikatsu_theme/images/inheritance/img005.jpg)
一棟の建物のうちに居住用とそれ以外の部分がある場合
一棟の建物のうち、居住用部分が含まれている場合には、特定居住用宅地等に該当する部分とそれ以外の部分とで減額割合を按分計算します。
![[部分] ごとに評価](https://akikatsu.net/wp/wp-content/themes/akikatsu_theme/images/inheritance/img006.jpg)
特定事業用宅地等と特定居住用宅地等を併用する場合
| ■特定事業用宅地等 400m2 |
} | 最大 730m2 まで適用 |
| ■特定居住用宅地等 330m2 |
※貸付事業用宅地等については除きます。